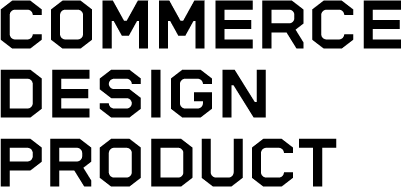「こんにちは」でござる☆
毎年10月19、20日の2日間にわたって開催される「べったら市」。今年は週末の土・日曜日と重なり、来年NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」放映の注目度が高まる中、例年になく盛り上がりました。ここ大伝馬町へ事務所を移転して毎年、べったらを食べることが恒例になりましたが、この甘く歯ごたえのある漬物を食べると、そろそろ師走を想うコマース鈴木です。


当社は「大伝馬町本通」沿いにありまして、この通りは江戸時代の目抜き通りです。この通りを少し北へ馬喰町の方へ歩いていきますと、蔦屋重三郎(1750年~1797年)の版元があった「耕書堂」跡地へと続きます。来年の大河ドラマの舞台になるのがここ大伝馬町界隈ということで、地元の期待も高まります!
本来は恵比寿講 (えびすこう)(20日)のための道具、供え物の塩鯛 (だい)、恵比寿大黒 (だいこく)の神像などを売る市だったそうですが、縄に縛った大根を若者らが「べったりつくぞぉ~、べったりつくぞぉ~」と叫びながら振り回したりしたことが「べったら市」の名称の由来だそうです(笑)

今年は町中にねずみ小僧や与力や岡っ引き、浪人が突然出現する嗜好が仕込まれていて盛り上がりました☆
突然「こんにちはでござる」とお侍さんに声をかけられたり、「どろぼーっ、どろぼーだ」と叫ぶ人がいるかと思うとねずみ小僧が柱の陰に隠れていたり、お縄になる捕り物を見たり、スマホで番所の人とのショットを撮影してくれたり、「映え」拡散も見込んだ現代と江戸時代が交錯した面白い風景が各所に見られました。

↑「こんにちはでござる」と浪人声が響く↑
さて、地元では来年の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢話~」へ向けて、様々な勉強会が催されています。10/4には第2回「蔦重勉強会」が常盤小学校で開かれ、私も参加してきました。
これまで見たこともない黄表紙の内容を紙芝居風に紹介してもらったり、自由で風刺に富んだ絵草紙のあれこれ。風俗規制に抵抗する版元たちの知恵比べなど、版画の歴史も時系列に説明を受けて大変興味深く学びました。
日本のサブカルの原点がこの江戸時代の版画や絵草紙にあるんですね~。
昔フランスでジベルニーのモネ邸を訪れた時、家中の壁に浮世絵が掛けられていて驚きました。モネの邸というより浮世絵美術館ともいえる多彩な絵師の作品が並んでいて、どんだけ浮世絵に憧れていたんでしょうね。鎖国の時代にどうやって入手したかわかりませんが、ジャポネーズの風は、モネ、マネ、ドガをはじめ、ゴッホ、ゴーギャン、ロートレックなど印象派以後の画家たちは、日本の浮世絵に大きな影響を受けました。それまで宗教画や肖像画の枠に囚われていた画材や画風が一機に浮世絵の影響で変化していく。何がそんなに天才たちを刺激したのか?・・江戸文化の「自由」な気風でしょうか?面白いですね♪

「蔦屋重三郎を学ぶ日本橋の会」は、蔦屋重三郎が開業した地本問屋「耕書堂」が現日本橋大伝馬町にあったことから、地元町会の有志らが立ち上げた勉強会。会長の濱田捷利さんは、1718(亨保3)年創業のはけ・ブラシの老舗「江戸屋」(日本橋大伝馬町2)12代店主。今後も定期的に勉強会や関連イベントを開催していくそうですが、次回の勉強会は12/14(土)に予定されているので、ぜひ参加してみてください。

当社の3つ隣のビル1Fに「江戸屋」さんはあります。紺色の大きなのれんが見印。
1718(亨保3)年創業のはけ・ブラシの老舗「江戸屋」さんは現在も営業中!
「江戸屋」>住所:東京都中央区日本橋大伝馬町2番16号
お近くへお越しの際はぜひお運びください。