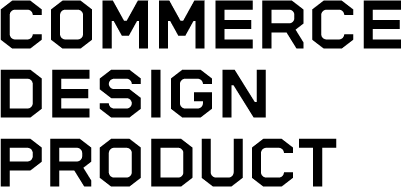13) 五 問われる市民としての条件
五 問われる市民としての条件
都市問題を議論する場合に、もっとも基礎的な条件となるのは、都市を構成している人間の性格であり、資格でもある。都市は人口の集まるところだと誰しもがいう。しかし単純な集まりではない。
わが国の場合には、日本人である限り、その国土内に自由に居住することを憲法は認めている。ただしそれが“住民”であるためには、住民台帳に登録する義務がある。それなら日本人といえば、すべて住民登録をしているかというと必ずしもそうではない。二一世紀の都市像のなかでは、少なくとも次の課題を検討する必要がある。
第一は、住民とは何かという原則論である。この点では、すでに述べたように、わが国では、住民登録という制度がその根拠となる。しかし、最近わが国で、外国人の滞在が多くなり、事実上の“居住”が増えている。居住しているものがすべて“住民”とはいえない。そこに国籍という別の規定がある。しかし、ここで注目しなければならないのは、最近国際問題にまで発展した日本が、単一民族であるという発想である。複合国家であるアメリカでは国籍を取得するときには、その名称は“市民権”といわれる。わが国では“市民権”といえば、別の権利のことになる。
なぜこのような規定をするかというと、社会学的にいうと、“住民”という表現には、一定の土地に、時間的にも生活的にも[i]“定着”することが必要だからである。住民は自らの生活を守るとともに、共存することで何等かの貢献もする。しかし原則としては“エゴイズム”が強い。生活防衛主義の傾向である。
第二は、似非住民である。すでに前項に述べたように、わが国では住民登録をしなければ住民としての利益を受けられない。しかしこの利益は最近ではあまり大きくない。戦時中から戦後しばらくはミニマムの消費生活が、住民の資格で与えられ“台帳”が交付された。最近は、このような手続きは必要としない。
地方では、生活が法律・規則によって束縛されることを嫌う傾向があり、この似非住民は都市の人口規模の増大に伴って増える。それは五年毎の国勢調査のときの登録人口、現在人口の差の変化に現れている。
“まちづくり”などでよく使う言葉に、“住民意識”という表現がある。それは、しばしば“市民意識”と混同して使われる。この点は極めて重要であり、さらに似非住民増大となると、正規の住民の社会的貢献の数値の計算にも影響を及ぼすものである。
第三は、都市の住民である。住民と市民とを区別すべきであるというのが私の年来の主張であり、二一世紀の“まちづくり”の基本的問題でもある。その考えは、次の理念に基づく。
“都市は人間がつくる”という西欧の言葉にこだわるわけでないが、事実都市は、そこに多年居住した人間によってつくられる。なるほど計画は、市なり町なりの構想によるが、それを“肉付け”するのは、あくまでも居住し、生活し、ある程度の経費を分担(シェアーという言葉を使う、シェアー・ホールダーといえば“株主”である。税金を“払う”のとは意味を異にする)した人である。
しかも、都市が成長すれば、法律に従い条例がつくられ、規則が実施される。それらを多数の住民が守りつづけて都市はつくられる。西欧では都市を“コミュニティ”という言葉で表現する。これは“地域生活共同体”だからである。共同生活が多年にわたって造った“都市”に無条件で居住を始めることは、共同体の本旨ではない。当然新しく市民になるものには、条件が課せられてよい。
私はこの条件こそが「都市憲章」だと思う、わが国では、「市民憲章」と呼ばれるものは多くある。“町を美しくしましょう”といった“約束規定”である。これは本来の憲章ではない。わが国では、日本国憲法によって地方自治法が広範な規定を設けており、一般に“三割自治”といわれるくらいに、自治の範囲が限定されている。
しかも、わが国では“都市”と“市”の概念と混同する場合が多い。“市”は上述の地方自治法によって“市制”をしいたもの、“都市”とは、必ずしも“市”のすべてを包括するものではない。
原則的にいえば、地方自治法の包括の内容は別として、少なくともそれぞれの市の「憲章」をもち、市民とは、その憲章に忠誠を誓うものを呼ぶとするのが正しいのである。
仮にある人が、都市に居を定め、単に住民登録によって市民と呼ばれる場合と、その都市憲章を守ることを誓っての市民とは、意識のうえにおいて異なる。
住民と呼ばれる場合には、ややもすれば、自らの生活環境の防衛を背景とするエゴイズムが働くが、憲章を守って市民という場合には、少なくとも公共の福祉のためには協力するといった共同体意識が生まれるはずである。住民と市民とのちがいはここにある。
第四は、都市の準市民である。この言葉自体が新しく感じられる通り、私の発想によるとともに、二一世紀都市形成の重要な課題となる。
都市の市民が原則として住民によって形成されるのは、当然であり好ましい状態である。しかし、都市のメタボリズムが高度化し、その頂点へのアメニティが強くなればなるほど、人口は都市に集中する。
戦後、わが国で国土総合開発計画は、三回にわたって構想され、現在は「三全総」から二一世紀を目前にして更に「四全総」が策定される時となっている。しかも、その伝統的な考えは、都市とくに大都市への人口の集中を防止し、地方への分散を意図したものである。それにもかかわらず、過去三〇年近くの時期は、大都市、とくに首都東京ならびにその周辺への集中を防ぐことは出来ないままになっている。
他方では、地方都市は、懸命に企業の誘致とともに、“故里帰り”、“故里づくり”を奨めているが、必ずしも十分な効果をあげていない。それは、原則として“市民”としての認識を欠くからである。
私は、もし都市が“故里”をテーマとするならば、その故里づくりに協力する者を“準市民”として処遇することであると思う。
別のことになるが、イスラエルは独立国であるが、国土の大半は砂漠、資源も乏しい。しかし海外には数千万人のユダヤ人がおり、その人々はイスラエルを“祖国”として、毎年多額の送金をする。この国はその「信託送金」によって国づくりを行っている。
この「信託市民制度」の対象になるのを“準市民”とよびたいのである。そして地方の都市の人口の対象のなかにも、この準市民を加える。たとえその住民が大都市に職場をもっていて、住居が市内になくても、準市民としての処遇を与える。準市民は一定額の分担(税金に相当する負担金)をする。地方都市の人口は維持され、財政も豊かにすることができる。
第五は、世界都市の市民である。世界の市民などというと、抽象的に聞こえるが、それは二一世紀に向っての都市像の一つである。“エキュメノポリス”を構成する市民のことである。この世界都市を構成する“市民”のことである。この“世界市民”ともいうべきものには二つの種類がある。
一つは、二〇世紀において、アメリカ・日本を中心に発達した「姉妹都市」に住む市民である。現在の段階において、姉妹都市は主として、都市の首長や議員などを中心にした友好親善の関係である。しかし国境をこえての連帯であることはいうまでもない。もし姉妹都市が“非核宣言”等をスローガンにして連繋すれば、共同の体制をとることも出来る。仮にそれにより災害が予防されるとなれば、“市民”としては同じ資格でなければならない。
二つは、国連が国際紛争や非常時災害等にあたっては、現在安全保障理事会の決議によって、国連軍等の組織をもって行動している。もしその対象地域が都市だとすれば、国連の措置や行動は、国境を越えた“市民”に対しての動きとなる。国連は、“国境”をこえ、“国籍”を離れた人々を“難民”の名において救援している。結局は難民の意志によってその居住する地域を定めているが、それがやがて一定のところに集結して都市をつくることも考えられる。
現在地球上には、“難民キャンプ”と言われるものによって、各地にスラムまがいの地域がつくられている。二〇世紀の都市には、都市に生活する住民・市民のメタボリズムによって、その地域内にスラムという地区が形成されている。
二一世紀には、好むと否とにかかわらず、国境をこえた難民が、世界のどこかに集結して“自由のまち”と名付けることがないとはいえない。
現にブラジルの首都ブラジリアが建設されたとき、建設のために国の内外から狩り集められた労働者達は、政府が飯場としてつくって与えた建物を嫌って、遥か郊外に仮小屋をつくって住んだ。建設事業が長年つづいたこともあって、この小部屋地区はスラム化し、さらにその中心が都市化し、結局は付近の一般住民も参加して“自由の都市”(シタ・デ・リベラ)という自然の町をつくったという。
市民といえば、“都市”が前提になるが、都市を離れた市民もあることは認識されねばならないのである。
「磯村英一都市論集III-IX日本の都市社会の未来像」より抜粋
「磯村英一都市論集III-VIII 人間回復のまちづくり理論」.pdf