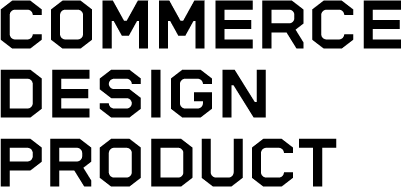第六 新しい市民社会の形成
第六 新しい市民社会の形成
二一世紀の都市を予測するに当たって、さらに重要な課題となるのは、都市とくに大都市が大きく機能変化をするなかで、“自治”と呼ばれる理論がどう変わるかである。
一 自治意識変容の課題
日本人が現在理解している“地方自治”は“与えられた自治”といえる。外国のそれには“闘いとった自治”といえるものがある。したがって、後者のような自治は、“国と市との約束・契約”ということができる。わが国のそれは、国が一方的に規定した“地方自治法”によって与えられたものでしかない。
日本の自治は今日でも“三割自治”などといわれるが、それは与えられたものであるからである。少なくとも“交渉”によるものであれば、そこに住民側に若干の主体性があるので積極的になる。しかし、憲法に基づいて“与えられた”法律となると関心は薄くなる。
自治意識の実態が具体的に表現されるのは、住民の参加の形式である“選挙”をどのような基盤で実施しているかにある。
第一は、日本の地方自治の基盤となる選挙権は、住民台帳への登録がその根拠となる。それは住民が日本の国土のなかで、どこに移っても“登録”すればよい。それ以外の条件はない。しかし都市の規模が大きくなればなるほど、登録しない住民の率が高いという事実がある。
第二は、日本人の選挙意識には、中央と地方を区別して考える。国会の投票は、地方のそれよりも重要であると考える。その結果、地方選挙の投票率は常に中央に較べて低い。大都市のなかには、投票者が有権者の半数にも充たないという現象が常識となっている。
第三は、大都市の住民のなかに、外国人が加わるようになる。それが特定の選挙区(主として都心地区)に集中し、登録する住民が少ないうえに有権者として登録出来ない外国人が増加するとなると、大都市において自治の運営に異質のものが生じてくる。
すなわち、都市とくに大都市は、地方自治の機能を拡充するという点からも、新しい視点から見直す必要が出てくる。
二 日本的自治意識の限界
わが国の地方自治が“与えられた自治”であることは、日本国憲法のタテマエからいって、当然であるといわねばならない。しかし、例を大都市制度にとって考えてみると、その発展の歴史のなかで若干主体性的反応のあったのを見つけることが出来る。
第一は、明治憲法の時代、東京市が新しい市制によって市長の選挙権が与えられながら、一○年余にわたって、特例として東京府知事が兼任をつづけた。これに対して当時の、東京市民は反対運動をつづけて、“特例廃止”を実現した。
第二は、太平洋戦争前であるが、政府は東京を「帝都」として特別な行政を実施するために、再三「都制案」を国会に提出したが、当時の東京市民は、“官選都長官”に反対しつづけ、ついに太平洋戦争という非常事態のなかで、“官選”を認めることになる。
第三は、戦後の民主主義のなかで、地方自治としては、府県も市町村も同じ趣旨の自治体として実現した。“地方公務員”としては、府県の職員も市町村のそれも同格となった。しかし大都市に関しては「特別市制」が認められ、府県の行政と部分的には、“平行”の立場としての実現が可能になった。大都市はその規定による特別市としての実現を運動しつづけたが、政府は府県知事の若干の権限の移譲によって、特別市制の適用を棚上げにし、そのような都市は「政令によって指定する」と規定され、現在でも“政令指定都市”という、およそ自治の理念とは縁のない呼称がつづいている。
以上のような経過からすると、わが国の地方自治の課題は、世界各国の自治意識と比較して、先進国としてふさわしい内容をもっているとは決していえないのである。
日本の自治体は二○世紀において、戦争完遂というかけ声の下に、一時は自治ゼロの状態がつづいたのである。それが“終戦”によって克ち得た地方自治は、その先頭に立つ都市とくに大都市のおどろくべき発展・変化のなかにおいても、いぜんとして戦争前にも見られないような実態のあることは、二○世紀の“市民”として、決して見逃すことのできない課題なのである。
わが国の地方自治は、その先頭に立つ都市の問題に関して、帰するところ、ほんとうの“市民意識”をもって対応するような市民が存在するか否かの一点に集約される。

三 新しい市民概念の認識
この点での問題は、“市民”という概念にハッキリした根拠を与えることである。日本国民として日本国憲法が規定しているが、○○市民としての根拠は必ずしも明らかでない。したがって、その根拠を確立することが必要である。
わが国の“まちの歴史”のなかで、国の支配者・権力者に対して、“対等の交渉”をしたものに、現在は大阪府にある「堺市」がある。その歴史のなかで、戦国時代の末期に、日本統一を図った豊臣秀吉に対して、堺の市民は“堺衆”を代表として、その地域の安全と施政について、“取引”をしている。
相手は戦国の武将、こちらは地域の商人、それがまがりなりにも“交渉”によって、地域の安全を維持したことは重要である。日本にも“市民の権利”が主張されたという例となるからである。
日本では、しばしば“市民社会”という言葉を使うが、これには問題がある。市民とは○○市の住民の意味であって、人間が集まっているから市民社会ということは出来ない。わが国では、比較的長い封建体制の時代には国民は、大名の“領民”であり、天皇親政となった明治の時代には、天皇の“赤子”であった。そこには住民の権利を守るような約束は、あったとしても一方的であり、恩恵的でしかなかった。
時たま催される“お祭り”のときだけは、僅かに“無礼講”といわれ“住民自治”が許されていた。したがって何等かの主張をもった市民社会はなかったのである。
明治の改革により、市区町村制が布かれたとき、たまたま“市”の呼称を許された自治体が、その住民を“市民”とよんだにすぎない。この点は二○世紀の時代においても、無批判のまま安易に市民社会という言葉が使われたのである。
したがって、もし“市民”または、“市民社会”という言葉を使うならば、その根拠となるものがなければならない。
四 市民としての根拠の変化
以上のように“市民”という言葉を追求してくると、次のような根拠が見られる。
第一は、日本の地方自治体制が規定しているように、ある“市に住む”という前提からくる住民即市民という考えである。しかしこのような理解は、仮にその意味で“市民社会”といったならば、市民や議員が選挙のときに呼びかける“市民”という表現以外の何ものでもない。呼ばれる者が、逆にその市に住んでいることを思い出す程度である。
第二は、住民という視点からの理解である。ある都市に住むということは、自らが登録しているいないにかかわらず現実の生活は、地域社会に人間関係をもち、近隣との接触もある。
このような傾向のなかでとりあげられた概念に、“日本的コミュニティ理論”がある。私の理解からすればコミュニティは、ゆるやかな人間関係の接触であり、権利・義務といった権力的なつながりではないとする。最近わが国でこの言葉が、内容もハッキリせずに安易に使われているのは、住民意識のなかに若干の連帯意識が芽生えたのではないかと見ることもできる。
第三は、市民という資格を住民との合意によって制定した憲章に基づく市民である。住民登録するときに市民となることを誓約する。“契約的”な意義の市民である。
私は、このような“契約市民制”は、すでに述べたように、居住しながら住民登録もせず、有権者であっても投票したことのないような、“似非市民”の増加を防ぎ、地域社会の連帯性、市民社会への参加を求めるうえから絶対に必要であると考える。それは住民と自治体との意識的連帯の紐帯となるばかりではない。市民社会形成の基盤となり、市民社会が国家体制のなかで、対等に話し合うことのできる前提となるからである。

五 都市憲章の設定
最近わが国でも、この言葉に似た表現がある。“市民憲章”。しかしこの二つの言葉はきびしく区別されねばならない。
第一に、市民憲章。特にわが国の都市でつくられているもののほとんどは、この名のものである。表現はやさしく見えるが、内容は、地方自治体の“首長”が、その行政の執行に当たって住民に協力して欲しいことを連記するにとどまるものが多い。いわゆる“○○しましょう”式のものである。
したがってこれは必ずしも憲章と呼ばない。市民として実践して欲しい項目を示唆したにすぎない。この市民憲章では、中央の行政事業等に積極的に対応できるような根拠とはならない。
第二は、都市憲章である。これが市民憲章と異なるのは、その内容が行政の担当者(首長である市長も含めて)はもちろん、一般住民も憲章の規定する内容は“市民としては守る”という約束の根拠とするものである。
二一世紀の都市の“市民”は、ある市に住民として居住する限りにおいては、その自治体の構築・事業について、ある程度の理解と協力をする約束をした住民をいうのである。
最近東京のような大都市には、外国人の居住者が多くなる傾向がある。この住民も、一定期間以上滞在するものは、その都市の憲章の規定のなかに“準市民”としての扱いを定め、若干の都市設備使用料に相当する分担を課してよいと考える。
少し古い話になるが、第二次世界大戦が始まる少し前、約一年間当時のドイツに留学し、ベルリンに滞在した。六ヶ月を過ぎたら市役所から呼び出しが来た。住民登録についてと書いてある。
日本の伝統からいえば、私は旅行者か滞在者である。少し長く滞在したが別に市民ではない。出向くと、理由は六ヶ月以上の滞在になると“準市民”の扱いをし、住民登録をするとともに、若干の経費を“分担”しろという。それは毎日道路を使い、水道・下水を使っている。ベルリン市は、その歴史のなかで何千万の市民が、何等かの貢献をして、今日の立派なまちになっている。それに若干の分担をすることは当然だという説明である。そしてサインをする前に、ベルリン市民の“憲章”の前文を読まされた。
“私はベルリン市の準市民となったことに誇りをもち、市の公共の福祉のためには協力する・・・・。以下の言葉は忘れたが、ベルリン市民としての誇りをもつということと、公共のためには協力するという二つの文句は、生涯忘れることができない。もし日本の都市のどこかで、このような都市憲章をつくり、新しく市民となる人々に、それを読むようにしたらどうだろう。否これだけは二一世紀を待たないで是非日本の都市で実現して欲しい課題の一つである。
“住民”という言葉には、自分の住んでいる環境に関心を集中する意味がある。“住民エゴ”という表現が使われるがそれを示している。しかし“市民エゴ”というのはほとんど聞かれない。市民という言葉で呼ばれる場合には、何等かの“連帯性”を考える。必ずしも自分の利害だけにはこだわらない。
イギリスは、現在経済的には斜陽といわれるが、地方自治については、“祖国”としての誇りをもつ。それはほとんどの都市が憲章をもっているからである。

IX 日本の都市社会の未来像.pdf (磯村 英一都市論集IIIより抜粋)