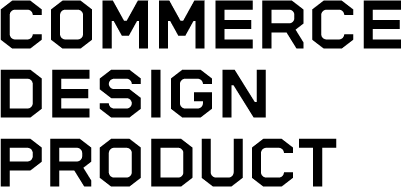第七 予想される都市社会の未来像
IX 日本の都市社会の未来像
第七 予想される都市社会の未来像
一九八〇年二回にわたって中国を訪れた。そこで見聞したのは、太平洋戦争後、いわゆる毛沢東支配が頂点にあった頃との大きなちがいである。毛専制の時代に聞いた“まちづくりの哲学”は、「就地主義」-すべてを地方都市で時給自足する-だった。曰く、「就地資源」、「就地生産」、「就地消費」。しかしまだこの都市に、そのまちづくりに必要な“資源”があるわけではない。しかし、この時代は毛語録をもっとも忠実に実現した。
ある地方では、これまで石油などは全く存在しなかった。これまで地質学者は、科学的にいってその都市に石油資源の存在しないことを明らかにしていた。しかし、それは“資本主義の論理”と排斥し、住民達は地域内の随所で石油の発掘を始め、ついにそれを実現したという。一時期は「その都市に学べ」という言葉が流行したという。
今回中国の都市を廻って見聞したのは、都市は、その立地する条件によって異なってきている。毛時代には、“流通”という機能が極端に限られていた。必然的に“就地主義”にならざるを得なかった。流通は、交通機関の発達によって可能となる。
一九八〇年代の中国は、流通経済の発達により、都市間の交流が激しくなり、それだけに中国の都市も、イデオロギーのいかんにかかわらず何等かの個性・特徴をもつように変わりつつある。
社会主義建国という体制のなかにおいても、都市は相互の交流が自由である限り、あらゆる機能の多様化のなかで、“個性の選択”が迫られていることは、世界的な視点からして自由主義諸国と軌を同じくしている。あえて都市自治に関する限り、“エキュメノポリス”を将来の都市像の目標として設定しようとするのも、この辺りにその論点がある。
以上のように、都市が国境をこえて、エキュメニカルな交流が多くなる当面の理由として次の二つがあげられる。
一 国内都市の連帯
第一は、都市という人間集団のなかにおいての“交流”の促進である。なぜ都市の人間が、あらゆる交通機関を使って交流するかというと、都市は原則として人間の直接の接触によってメリットを生む社会だからである。
人口一〇万人の都市は、その住民の接触の度合いによっては一○万をこえる評価が与えられる。二〇世紀内のメカニズムは、この都市社会の生む“超過エネルギー”を具体的にとらえることは出来ないかもしれない。しかし将来は、人口密度、接触の頻度、対話の濃度等が具体的に測定され、それが都市社会の“生産指数”-それは経済的な意味だけでなく文化的なものも加えて-となって、他の都市との交流の資源となることが予想される。
第二は、個々の都市生産指数は、直ちに“情報”となって他の都市に伝達される。都市相互の間に“指数の格差”があれば、具体的な交流によって、ある程度の平均化が図られる。
たとえば、ある都市で製造された食品は、直接(交流)、間接(情報)によって他の都市の市場となる。一つの国内においての都市相互の“競争と共存”の論理である。
二 国際都市の連帯
一九八○年代の先進国のテレビは、それぞれの国の“経済市況”を刻々に報道する。情報が発達した結果である。しかし同じ経済指標であっても、その内容を異にする。たとえば、テレビ・ラジオは対米ドルの円相場について東京の市場の結果を報道する。同時にロンドン市場での円相場も知らされる。ところがその数値は必ずしも同じではない。相互に高低の差がある。それは“円相場”につながるいろいろな“社会的・経済的・政治的要因”が緊密に作用して“円相場を創造する。”それが東京とロンドンで異なるということは、二つの都市社会の機能が、“競争と共存の理論”のなかで、独自の社会を構成する必要性のあることを立証することになる。
これは“円相場”という一つの指標による例示であるが、それは必ずしも経済事業だけではない。科学・技術の関係においても同じである。世界各国の都市には大学があり、研究所がある。科学の社会というと、いかにも閑静な間接的な接触を予想するが必ずしもそうではない。直接的には研究室における対話、図書室における情報資源の閲覧等が科学・技術の進歩の原点となる。しかしコンピューターを通して伝達される一つの文章、一冊の本が意外な“創造の原点”となる。それは国境を越えての交流である。“情報は聞かれる”と同時に“情報には将来がある”という背反する論理の存在するのは、そこに人間の個人としての能力と集団としての能力を保持するという二○世紀の人間性の一面を示していると説明することもできる。
三 都市社会の自治行政
都市社会における住民・市民の生活態様の変化は、当然その行政理念に影響を及ぼす。都市の市民社会が、いちじるしく人間の主体性・個性化に重きを置くようになる限り、都市の行政は、そのサービス性を増強することになる。
わが国の行政は中央政府を中心にして一九八○年代に、いわゆる“行政改革”の名においてその体制の見直しに努力した。それは国の行政が官僚化し、国民へのサービスがいちじるしく硬直化したことが原因である。そしてその改革に当たって語られたのは、行政の活性化であり、効率化である。現実の方向としては、民営化することに集約されるが、その方向は地方行政、都市自治についてもちがいはない。二一世紀を見透かせばむしろ地方自治体の機能こそが、先行して改革される必要があった。国の行政の非現実化のシワヨセが地方行政に反映していることが分かるからである。
以上のような状況のなかで、地方行政が当面改革しなければならないのは市民へのサービス、同じ行政をする府県、そして国の行政にどのように対応するかである。
第一の市民に対しては、都市の事務・事業がいちじるしくサービス性をもつことから、すでに述べたように市民サービスと“経営の理念”に基調を求める。
一口に自由というが、その考えは市民自身にも求められる。人間の居住生活のアメニティは、生活が第三者の指示・介入を受けない“自立・自主”であることである。むしろ居住する地域の行政サービスなどが意識されないような状態こそ理想の姿である。したがって行政サービスは、むしろ市民としての登録に際しての“契約”に規定されるようになる。
これまでの都市行政は、その行政理念が、住民・市民のニーズに答えるのではなく、むしろ国または府県のタテ割的な行政の下請けとして実施されてきた。都市がその地域のなかにコミュニティ的な自主サービス・エリアをもち、市民のニーズに敏感に反応するには、行政サービスを“契約の理念”によって再構築する必要がある。
市民から税金をとりたてて、それを行政の首長等の恣意的構想によるサービスに使用するという現状では、市民のニーズにどのように対応しているかが明らかでなくなるからである。
例えば、戦後わが国でも実施されるようになった“コミュニティ・チェスト”(日本では共同募金と訳す)は、本来は住民の連帯意識が直接福祉事業に反映することに意義があった。善意で箱に入れられた金が、身近な福祉施設のサービスに加えられてこそ意味がある。それがわが国では、個人の善意はほとんど姿を消して、地域団体の“予算”のなかから供出される。明らかにサービスの行政化・企画化による“善意の喪失”となる。
二一世紀の行政は、住民・市民への直接のサービスである限り、施策に対する反応は“経営の論理”でなければならない。そこにはいささかの“役所的・官僚的権威”の介入も許されないのである。
第二は、以上のような市民へのサービスは都市自治の範囲が拡大し、サービスの内容が合理化することから、それぞれの自治体のみですべてを提供することは不可能の状態が生まれてくる。
太平洋戦争後、新しい行政の範域として、“圏”という呼称が使われた。それは上水・下水など、府県や市町村の行政区画に限られた範囲のものから、首都圏・近畿圏など市町村はもちろん府県の範域をこえた区域の指定が行われた。それは、これらの広域行政が明治以降の府県・市区町村の範域に調和しないために、地方自治の行政範囲を離脱しての姿なのである。
本来ならば、関係市区町村の合併かまたは行政の連帯によって実施さるべきものである。具体的には市町村の範域が、新しいサービスを実施するのに、さまたげになっている結果だからである。それに加えて、自治行政がその行政能力において、高度化し、複雑化する技術に対応できないという面も圏域形成の原因となっている。しかし、すくなくとも二一世紀には、現在の広域行政に対応できるように、地方行政の自治能力の水準を高める必要があることはいうまでもない。
第三は、国と自治体との行政サービスの分担の明確化である。わが国の地方自治体は、都道府県市区町村に加えて、政令指定都市という特別な組織に分かれている。この行政区画は、明治の改革以降それぞれの理由によって設定されている。しかし、少なくとも日本の歴史に一大時期を画した太平洋戦争後再三行われた改革のなかで、この複雑な制度の改革が行われず、かえって、圏域行政が増加し、さらに“公社行政”までが加わっている。このことは当然“行政改革審議会”の検討課題だったと思うのであるが、全く触れられなかった。いわんや、地方自治、とくに“都市自治”の位置づけが論議の背景とならなかったのは、“行革審”の理論的貧困といっても差し支えない点である。
なぜならば“行革審”は、別に地方行革という課題を設定し、そこには中央の行革方針に準拠する方策を提言しながら、中央行政の一部を“移管”することで終わっている。それに対して、地方自治体は、財源の裏付けなき事務・事業の移管には消極的な態度を示している。
この点で重要なのは、住民・市民のニーズの増加に対して、地方とくに都市行政がどれだけ主体的にサービスが出来るか、それを実施できる財源はどうするかの点である。理論的には、地方自治はそれぞれの行政単位でどれだけの主体性が発揮できるかの位置づけである。
日本の地方自治、とくに急速な発展を見せている都市行政の水準は、府県段階の行政に併行し、大都市はより高いサービスの能力を持っている。理論的に地方自治は、住民・市民に対してそのサービスの範囲を“公約”可能の段階に来ている。都市行政は、国の行政の分担執行ではなく、かなりの部門の“自主実施”が可能となっている。少なくとも府県と大都市との間に“二重行政”が出現している実態は、調整されべき重要な課題である。
“行政改革”は、日本の社会が二一世紀を迎えるに当たって、その準備のための絶好の機会であった。それが結果において、いわゆる行政の大半―それも住民・市民・国民に直結する―を占める地方行革が中途半端に終わったことは遺憾至極である。

IX 日本の都市社会の未来像.pdf (磯村 英一都市論集IIIより抜粋)